バイオセンシング技術の一つであるELISA(酵素結合免疫吸着法)は、特定のタンパク質や抗体を検出するための強力な手法です。本記事では、ELISAの基本的な用語解説とその使い方について初心者向けにわかりやすく説明します。
ELISAとは?
ELISAは、酵素結合免疫吸着法の略で、特定の抗原や抗体を検出するための生化学的手法です。主に医療や研究の分野で利用され、感染症の診断や、免疫応答の評価、食品中のアレルゲン検出などに用いられます。
ELISAの基本原理
ELISAの基本的な原理は、抗原と抗体の特異的な結合を利用しています。サンプル中の抗原がプレート上に固定された抗体と結合し、その後に酵素標識された二次抗体が結合します。最後に、酵素の基質を加えることで色が変化し、抗原の量を定量できます。
ELISAの種類
ELISAにはいくつかの種類がありますが、主に以下の3つが一般的です。
1. **直接ELISA**: 抗原をプレートに直接固定し、酵素標識された抗体を加える方法です。シンプルで迅速ですが、特異性が低い場合があります。
2. **間接ELISA**: 抗原を固定した後、一次抗体を加え、それに結合する酵素標識二次抗体を使用します。この方法は特異性が高く、感度も向上します。
3. **競合ELISA**: サンプル中の抗原と標準抗原が競合して抗体に結合する方法です。定量的なデータが得られやすく、特に低濃度の抗原を検出するのに適しています。
ELISAの手順
ELISAを実施する際の基本的な手順は以下の通りです。
1. **プレートの準備**: ELISAプレートに抗体を添加し、一定時間インキュベートします。これにより抗体がプレートに固定されます。
2. **サンプルの添加**: 検出したい抗原を含むサンプルをプレートに加え、抗体と結合させます。
3. **洗浄**: 結合していない抗原を洗い流します。
4. **二次抗体の添加**: 酵素標識された二次抗体を追加し、再度インキュベートします。
5. **再び洗浄**: 再度、結合していない抗体を洗い流します。
6. **基質の添加**: 酵素の基質を加え、色の変化を観察します。
7. **結果の測定**: 分光光度計を使用して、色の濃さを測定し、抗原の濃度を定量します。
ELISAの利点と欠点
ELISAの利点には、高い感度と特異性、比較的簡単な操作、定量的な結果が得られることが挙げられます。一方で、欠点としては、時間がかかることや、試薬のコストがかかることがあります。
ELISAの応用例
ELISAは多くの分野で応用されています。例えば、感染症の診断(HIV、インフルエンザなど)、アレルギー検査、ホルモン測定、ワクチンの効果評価などが挙げられます。特に、早期診断や定量的なデータが必要な場合に非常に有用です。
ELISAは、特定の抗原や抗体を検出するための非常に強力な手法です。基本的な原理や手順を理解することで、さまざまな分野での応






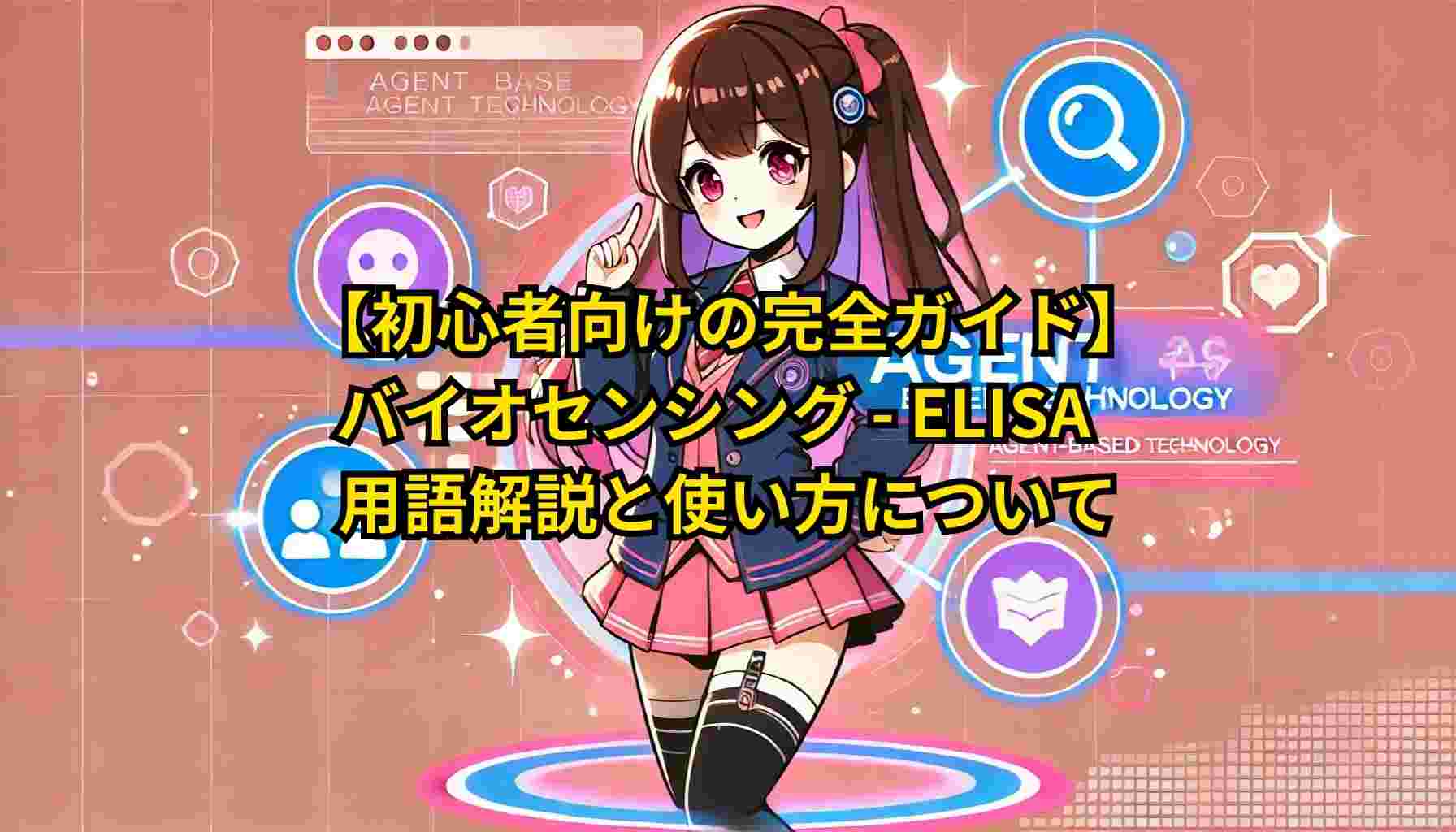


コメント